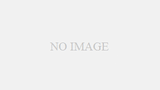- (12月13日)FRBが金利据え置き
- (12月7日)日銀の植田総裁が「年末から来年にかけ一段とチャレンジングになる」と発言
- (11月1日)FRBが金利据え置き
- (10月31日)日銀が長期金利の上限を「1%をめど」に
- (10月26日)中国の李克強前首相が死去
- (10月25日)ドイツが日本を抜いて世界3位の経済大国に
- (10月7日)ハマスがイスラエルに大規模な攻撃
- (9月21日)FRBが金利据え置き
- (8月30日)国内の金の小売り価格が初の10,000円/g超え
- (8月18日)中国恒大集団が米国の裁判所に連邦破産法15条の適用を申請
- (8月1日)米国債が格下げ
- (7月27日)FRBが0.25%の利上げを決定
- (7月12日)米国の6月の消費者物価指数は前年同月比3.0%増
- (7月10日)トルコのエルドアン大統領がスウェーデンのNATO加盟に同意
- (6月24日)ワグネルがロシアに対し武装蜂起
- (6月14日)FRBが政策金利の据え置きを決定
- (6月13日)米国の5月の消費者物価指数は前年同月比4.0%増
- (5月29日)日経平均が33年ぶりの高値を記録
- (5月28日)米債務上限問題について、バイデン大統領とマッカーシー下院議長が合意
- (5月25日)1ドル140円の円安
- (5月19日)日経平均がバブル後の最高値を更新
- (5月19日)広島市でG7開幕
- (5月10日)米国の4月の消費者物価指数は前年同月比4.9%増
- (5月8日)新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが5類に引き下げられた
- (5月4日)FRBが0.25%の利上げを決定
- (5月1日)米ファースト・リパブリック銀行が破綻
- (4月19日)国連人口基金が世界人口白書2023を公表
- (4月10日)日銀の植田和男新総裁が就任会見
- (4月5日)台湾の蔡英文総統が訪米。マッカーシー下院議長と会談
- (4月4日)フィンランドがNATOに加盟
- (3月22日)FRBが0.25%の利上げを決定
- (3月20日)中国の習近平国家主席がロシアのプーチン大統領を訪問
- (3月20日)スイスの金融最大手UBSがクレディ・スイス・グループを買収
- (3月12日)米シグネチャー銀行が閉鎖
- (3月10日)米シリコンバレー銀行が経営破綻
- (3月8日)米シルバーゲート銀行が事業の清算を公表
- (3月7日)パウエルFRB議長が利上げ幅の再拡大を示唆
- (3月6日)徴用工問題で韓国から賠償金を「肩代わり」する提案
- (2月24日)日本の1月の消費者物価指数が前年同月比4.2%増
- (2月14日)米国の1月の消費者物価指数は前年同月比6.4%増
- (2月6日)トルコ南部でM7.8の地震
- (2月3日)米国の1月の失業率は3.4%
- (2月2日)ECBが0.5%の利上げを決定
- (2月1日)FRBが0.25%の利上げを決定
- (1月25日)アメリカとドイツが、ウクライナへの戦車の供与を発表
- (1月6日)10年もの国債の利回りが0.5%まで上昇
(12月13日)FRBが金利据え置き
(12月7日)日銀の植田総裁が「年末から来年にかけ一段とチャレンジングになる」と発言
(11月1日)FRBが金利据え置き

2回連続の据え置き。長期金利の上昇がインフレ抑制をもたらすと判断したか。
(10月31日)日銀が長期金利の上限を「1%をめど」に
(10月26日)中国の李克強前首相が死去
(10月25日)ドイツが日本を抜いて世界3位の経済大国に

IMF発表。国民1人当たりの名目GDPはドイツ52,824ドルに対して日本33,950ドル。円安やインフレだけが原因ではないよな…
(10月7日)ハマスがイスラエルに大規模な攻撃

1973年の第4次中東戦争以来の規模。
レバノンのヒズボラとの戦闘も発生。
(9月21日)FRBが金利据え置き

政策金利は5.25~5.50%で据え置き。24年末は5.1%の予想。
23年の経済成長率を0.4%から2.1%へ上方修正。ソフトランディングへの自信の表れか。
(8月30日)国内の金の小売り価格が初の10,000円/g超え

世界的な経済の先行き不安と円安が原因
(8月18日)中国恒大集団が米国の裁判所に連邦破産法15条の適用を申請

日本の民事再生法に相当。
過去2年間の純損失は11兆円に上る。
中国の7月CPIは前年度比-0.3%と、2年ぶりに低下。中国人民銀行は利下げ。
(8月1日)米国債が格下げ

フィッチ・レーティングスにより外貨建て長期債がAAAからAA+に格下げ。
財政悪化予想と債務残高の増加等が理由。
5月に格下げの見通しを公表していたが、米国株価は下落。日本株価は大きく下落。
前回のS&Pによる格下げ(2011年)では、米国債利回りは低下したが、今回は上昇した。
(7月27日)FRBが0.25%の利上げを決定

政策金利は5.25~5.50%に。ターミナルレートを超えた。
パウエル議長は「スタッフはもはやリセッションを予想していない」と述べた。
(7月12日)米国の6月の消費者物価指数は前年同月比3.0%増

5月の4.0%から低下。
コア指数は4.8%と依然高い。
次回の利上げは見送られるか。
(7月10日)トルコのエルドアン大統領がスウェーデンのNATO加盟に同意
(6月24日)ワグネルがロシアに対し武装蜂起

ロシアのミサイル攻撃によりワグネルの兵士が多数死亡したとしてモスクワに進軍。25日には撤収。
ロシアは超法規的に不問とし、創設者プリゴジン氏はベラルーシに出国。
(6月14日)FRBが政策金利の据え置きを決定

11会合ぶりの利上げ停止。CPIは減速しつつも高い水準。次回の利上げを示唆した。ターミナルレートはいったん守ったということか。
(6月13日)米国の5月の消費者物価指数は前年同月比4.0%増
(5月29日)日経平均が33年ぶりの高値を記録

米債務上限問題の合意を好感。円安で海外からの投資が増加。
(5月28日)米債務上限問題について、バイデン大統領とマッカーシー下院議長が合意

議会での採決はこれから。2025年1月まで債務上限を停止。歳出に上限を設けることによる経済への影響に注目。
(5月25日)1ドル140円の円安

米利上げ終了観測の後退と米債務上限問題が原因。米国がデフォルトになると債券が償還されない=ドルが不足すると予想されてのドル買い。
債券が売られる=債券価格が下がる=金利が上がる=ドル高要因でもある。
(5月19日)日経平均がバブル後の最高値を更新

終値が3万808円。33年ぶり。
米国経済がハッキリしないから、金融緩和継続スタンスが明確な日本が投資先として選ばれたか。
(5月19日)広島市でG7開幕
(5月10日)米国の4月の消費者物価指数は前年同月比4.9%増

5%を下回ったのは約2年ぶり
6月FOMCで利上げ終了もあり得るか
(5月8日)新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが5類に引き下げられた
(5月4日)FRBが0.25%の利上げを決定

再び銀行破綻よりインフレ抑制を優先
政策金利は5.00~5.25%に。ターミナルレートに到達したものの、3月CPIは前年同月比+5.0%でインフレは根強い。
利上げ終了(楽観)と継続(悲観)が入り混じっている。
5月10日発表の4月CPIに注目。
(5月1日)米ファースト・リパブリック銀行が破綻
(4月19日)国連人口基金が世界人口白書2023を公表

世界人口はすでに80億人に到達。
2023年の日本人口は2022年と比べ230万人の減少見込み。
2023年中にインドが中国を抜いて人口1位になる見込み。
(4月10日)日銀の植田和男新総裁が就任会見

金融緩和は継続の姿勢
短期的には円安要因
(4月5日)台湾の蔡英文総統が訪米。マッカーシー下院議長と会談

一方で馬英九前総裁は中国訪問
(4月4日)フィンランドがNATOに加盟

スウェーデンの加盟についてはトルコとハンガリーが未批准。
(3月22日)FRBが0.25%の利上げを決定

政策金利は4.75~5.00%に。
銀行破綻よりインフレ抑制を優先した。
(3月20日)中国の習近平国家主席がロシアのプーチン大統領を訪問
(3月20日)スイスの金融最大手UBSがクレディ・スイス・グループを買収

米シリコンバレー銀行破綻の余波。買収により国際的な金融不安は沈静化
(3月12日)米シグネチャー銀行が閉鎖
(3月10日)米シリコンバレー銀行が経営破綻

債券比率が多く、政策金利上昇による債券価格の下落で含み損が増大していた。
(3月8日)米シルバーゲート銀行が事業の清算を公表

2022年11月のFTX経営破綻後に預金が引き揚げられ、自己資本比率が規制値の5%に迫っていた。
(3月7日)パウエルFRB議長が利上げ幅の再拡大を示唆

2月度の雇用統計や消費者物価指数次第か。
(3月6日)徴用工問題で韓国から賠償金を「肩代わり」する提案

林外相は評価。バイデン米大統領も即日評価コメント。
ホワイト国復帰は別問題のはずだが…
日本が代わりに何を得たのか注目。
(2月24日)日本の1月の消費者物価指数が前年同月比4.2%増

41年ぶりの上昇率。
円安や資源高によるコストプッシュ。
日銀の目標2%を上回っているがどう動くか?
(2月14日)米国の1月の消費者物価指数は前年同月比6.4%増

減速しつつも市場予想を上回った。
賃金や住居費の上昇が牽引。インフレ傾向は根強い。
(2月6日)トルコ南部でM7.8の地震
(2月3日)米国の1月の失業率は3.4%

53年ぶりの低水準。利上げ終了を見込んでいた市場を裏切った。インフレ抑制はまだ済んでいない。さらなる利上げが見込まれる。
(2月2日)ECBが0.5%の利上げを決定

政策金利は3.00%に。
1月の消費者物価指数は前年同月比8.5%で依然高い。
(2月1日)FRBが0.25%の利上げを決定

通常の利上げ幅に戻った。結果、4.5~4.75%に。
議長は利上げの継続を示唆。
ダウは上昇。軟着陸を予想か。
(1月25日)アメリカとドイツが、ウクライナへの戦車の供与を発表

アメリカの参加は、ドイツ単独でないことのアピールのためか。
(1月6日)10年もの国債の利回りが0.5%まで上昇

国債が売られる→価格が下がる→利回りは上がる、という関係。市場は政策金利の上昇を予想している?
昨年12月20日に日銀が長期金利の上昇を0.5%まで容認する発表をしていた。